“良い臨床家を諦める”という覚悟 ──佐賀大学総合診療部同門会に参加して
同門会では、研究の一般講演と、佐々木先生の特別講演がありました。本村先生の非感染性炎症性疾患についての研究も臨床にすぐに応用できそうな内容で刺激的でした。また現在当院にも関わっていただいている香月先生と、東邦大学総合診療部の佐々木教授の講演もありました。
香月先生の発表では、大学での研究をチームで行うというお話。研究と臨床、研究と学生、研究と…と様々なポイントでコラボレーションしつつ、研究マインドを育てているとのことでした。そのかいもあって英語の論文は毎年20本発表できている、佐賀大学の中でもまずまず発表できている方だとのことでした。
「一人一症例にに取り組むことを課題としている!」とプレッシャーが会場内に響き渡りました(笑)。その積み重ねが教育にも、研究にもつながっていく。研究者としては、若手に学位取得の道を提示しながら、チームで支える姿勢を強調されていたのがとても香月先生らしく、背筋が伸びる思いでした。
その後の講演で登壇されたのが、東邦大学の佐々木先生でした。
タイトルは「なぜ大学で総合診療をやるのか」。
一番、なるほどと共感したフレーズは、
「私は“良い臨床家であること”を諦めた。」
この覚悟はすごい!ことだと思いました。大学病院より市中病院のほうが総合診療医の能力は正直生きるんですよね。臨床能力って言うのはある意味医師のプライドの一つではあるのですが、割り切れるところが心より凄いと思いました。いや、ジレンマを感じているとのことでしたので、割り切れてないのかもしれませんが。
大学病院という環境で、研究・教育・臨床の“ジャグリング”を続けるなか、自分自身の臨床力が低下していく実感と向き合いながら、それでも「育てる」ことを選び続ける──。これは並の覚悟ではありません。ただし、教育のスキルっていうのは、医師のキャリアでいうと汎用性が乏しいんですよね(現時点では)。
そして佐々木先生は、続けてこう話されました。
「患者さんの紹介を受けたら、一生懸命診察する。主治医と一緒に心配する。その姿勢を、私は学生に伝えたい」
私はこの言葉に、強く共感しました。医の基本的姿勢ですよね。というより、ビジネスマンとして、大人としての基本的姿勢でもあります。一人ひとりの患者さんの物語に耳を傾け、生活の背景ごと診る。そして、その人に寄り添いながら「チームで」医療を提供していく。
佐々木先生はまた、世代別の総合診療医の変遷についても言及されました。
-
第1世代:専門医から転身した先駆者たち
-
第2世代:総合診療を受け入れ、生き生きと働く市中病院の実践者たち
-
第3世代:研究にも取り組む新たな知の担い手たち
第4世代(Y先生仮説):他の学部とのコラボレーションを企画できる
そのなかで、「大学に総合診療医がいる意味」として語られたのが、教育者として「初期学習を間違ってはいけない」という警句でした。総合診療は“何でも屋”ではない。必要なのは、「一緒に心配する医療」「病院のインフラとして支える役割」であり、それを学生たちに示すことが大学の総合診療医の責任ということでしょう。
開業医として教育に関わる時に気をつけたほうが良いことをアドバイス頂きました。してほしいことは「自然な医師としての姿を見せてくれるだけで良い」とのこと。してほしくないことは、ネガティブな心理、社会的要因を軽視してほしくないこととのことでした。
佐々木先生が「大学で育てること」に全力を注がれているように、私たちもまた「現場で育てること」に対して責任を持っていたいと思います。
懇親会では、O先生と「開業医のリアル」について語り合いました。経営、制度対応、限られた資源の中でどうバランスを取るか。一見、佐々木先生の話とは対照的ですが、「医療を絶やさない」「続けていく」ための工夫という意味では、根底で通じているように感じます。
大学での教育と研究。地域での実践。その両輪がそろってこそ、総合診療は未来に残る。
前Y教授の「今日は日本が滅びる日だとのことですが、世界は滅んでも総合診療は生きる」に大笑いしました。
そして、今も教育に、臨床に、静かな覚悟で向き合い続けている先生方の姿勢は、私にとって何よりの学びでした。疲れていたのに、少しも眠くならない一日でしたが、勿論帰ったら爆睡です…。
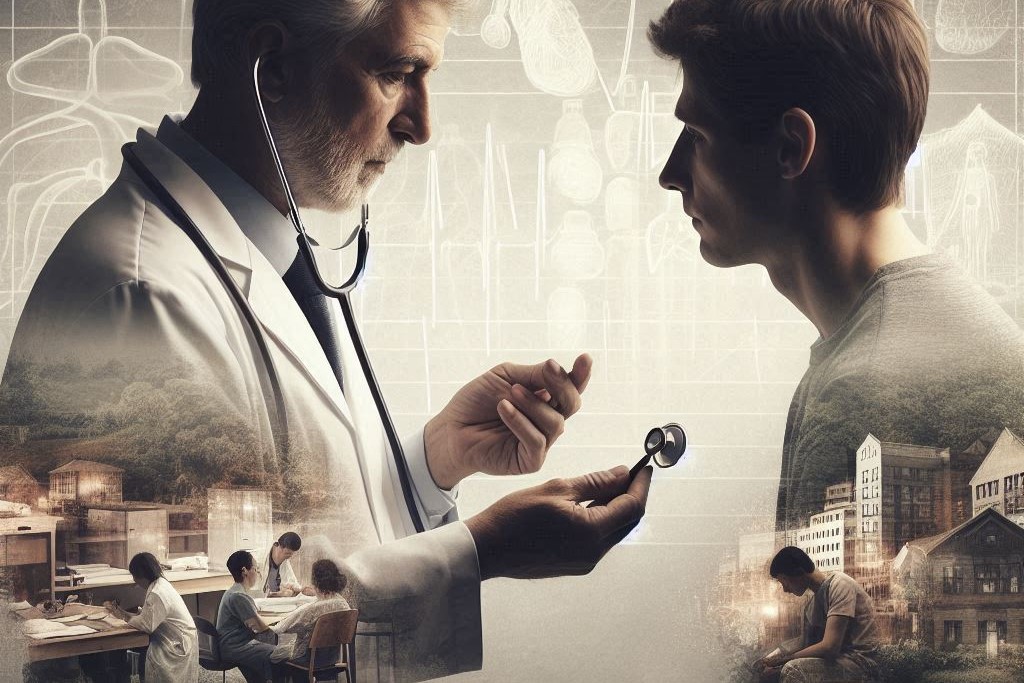



コメント
コメントを投稿