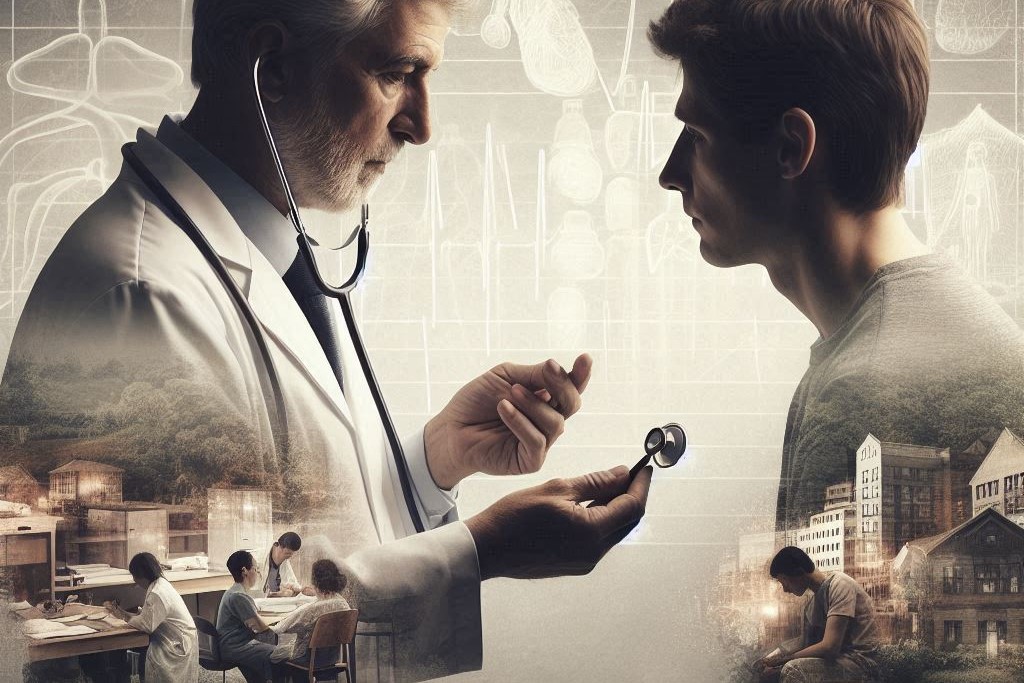悪人

本当はサプライチェーンマネジメントの記事を書いていたのですが、進まない進まない。Geminiさんと一緒に学びましたが、難しい難しい。一休み一休み。 ってことで、今週末は選挙!3連休の真ん中にして投票率を下げている!!ワタクシ、土曜日も月曜日も仕事なので1連休ですからお気になされず。 さて、ネットを開けば、「医者は儲けすぎだ」「医療費が国家財政を圧迫している」といった言葉が並びます。(財務省さん、感情的にしすぎですよ?)選挙の季節には、候補者が「社会保障費が財政を食い潰している」「医療費の無駄を削減しなければ日本が沈む」と議論がネットで拡散されているのを、昼ご飯をかきこみながら見ております。 けれど、医療の現場は、そうした光景とは対照的です。私たちは、日々、患者さんの身体と生活、感情に寄り添い、どうすればその人らしく過ごせるかを考え続けています。便利なシステムも人工知能も、最後に患者のそばにいるのは人間の手と声です。夜間に呼び出されても、ターミナルの現場でも、誰かの人生の傍らに立つ仕事。それが医療職、介護職です。 なのに、社会の一部からは、まるで「無駄遣いの元凶」のように語られるのはいささか辛い。鈍感力が強い私が答えるので、共感力の高い医療関係はより辛いのでは?と思いを馳せております。そのたびに、真面目に働いている人たちが、何かを失っていく気がしてなりません。いや、現実的に真面目に働いている看護師さん介護士さんたちは、失望して現場を離れております。 (引用:漫画「鋼の錬金術師」) 「賃上げしても社会保険料で消える」は本当か? 近年、「給料が上がっても社会保険料が全部持っていく」といった声が強まっています。2024年4月には『日本経済新聞』が「賃上げ、社会保険料に消える」と報じ、社会に大きな波紋を呼びました。 このフレーズは、生活実感に寄り添うようでいて、実際には誤解を招く表現です。総務省の 「家計調査」 によれば、39歳未満の勤労世帯では、2018年から2024年の6年間で月額社会保険料は約6,200円増加しましたが、同期間に世帯主収入は33,341円増加しています。保険料の増加はその18.6%にとどまり、収入の大半はきちんと可処分所得として手元に残っているのです。(経理・総務をしている方なら当然ご存知ですが、保険料率が18.3%だからですね) 会社が社会...

.png)